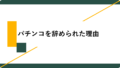投資の世界には、時に信じられないようなドラマが起こります。
つい先日、私はそのドラマの主人公になってしまいました。
9月18日に発売された四季報プロ500の秋号。
私はその情報を基に、新たなポートフォリオで秋の相場に臨みました。
<関連記事>【実践編】個別株銘柄の選び方×逆指値トレードのリアルな方法
すると、どうでしょう。
212A フィットイージーや4633 サカタインクスなど、購入した銘柄が軒並み上昇。
9月末までのわずか1週間あまりで、含み益は10万円を超えていました。
「今回の銘柄選定は、完璧だったかもしれない…!」
そんな浮かれた気持ちで10月を迎えた私を待っていたのは、悪夢のような現実でした。
保有株が、次々と暴落。
あれよあれよという間に含み益は消え去り、-1万円、そして気づけば評価損益は-6万円に。
天国から地獄とは、まさにこのことです。
企業の悪材料が出たわけでもない。
市場全体がパニックになっているわけでもない。
(自民党の総裁選とかはありましたが・・・)
「一体、何が起きているんだ…?」
原因を調べた結果、私は一つの要因にたどり着きました。
それは、多くの銘柄に共通していた「配当」というイベントでした。
この記事では、私と同じように「理由なき株価下落」に怯えるあなたが、冷静に状況を判断できるようになるための知識を、私の失敗談とともにお届けします。
この記事で説明している配当だけが株価に影響しているわけではありません。
あくまで、”株価を決める一つの要因“程度にご理解ください。
暴落の犯人。「配当権利」をめぐる株価のカラクリ
私の保有株を暴落させた犯人。
それは、9月末に集中していた「配当の権利落ち日」でした。
私が保有する銘柄のうち、
- 1893 五洋建設
- 7059 コプロ・ホールディングス
- 7994 オカムラ
- 8803 平和不動産
これらの銘柄は、いずれも9月末が配当の権利確定月でした。
そして、この「配当」というイベントの前後では、株価が非常に特徴的な動きをするのです。
この仕組みを知らないと、私のようにパニックに陥ってしまいます。
まずは、3つの重要な「日」について、算数レベルで理解していきましょう。
3つの「日」を制する者が、配当を制する
ここでは、9月末決算の会社を例に見ていきます。
① 権利付最終日(9月26日(木)など):配当をもらう権利が得られる最終日
この日までに株を買って、保有していれば、配当金をもらう権利が確定します。
配当が欲しい投資家たちの「駆け込み需要」で、株価が上がりやすい日です。
② 権利落ち日(9月27日(金)など):配当をもらう権利がなくなる日
権利付最終日の翌営業日です。
この日に株を買っても、もう今回の配当はもらえません。
株の価値から「配当金相当額」が差し引かれた状態になるため、理論上、株価はその分だけ下落してスタートします。
これが「権利落ち」です。
③ 権利確定日(9月30日(月)など):株主名簿に名前が載る日
会社が「この日に株を持っていた人」を株主名簿に記録する日です。
実際に配当を受け取るためには、この日に株主である必要がありますが、日本の株式市場のルール上、①の権利付最終日までに買っておけばOKです。
私たち投資家が、この日を強く意識する必要はあまりありません。
一番重要なのは、①と②の関係です。
たった1日の違いで、配当がもらえるかもらえないかが決まり、それが株価に直接反映されるのです。
【一般的パターン】配当権利確定から次の確定までの株価の旅
この3つの「日」を軸に、株価がどのような値動きをするのか、一般的なパターンを見ていきましょう。
もちろん、全ての銘柄がこう動くわけではありません。
ですが、大きな流れとして知っておくと非常に役立ちます。
フェーズ1:権利付最終日に向けて、株価は上昇しやすい
権利付最終日が近づくにつれて、「配当が欲しい」と考える投資家が増えてきます。
そのため、買い注文が優勢になり、株価はジワジワと上昇していく傾向があります。
私が9月末までに+10万円の利益を得られたのは、この上昇気流にうまく乗れたからだと考えられます。
フェーズ2:権利落ち日に、株価は「落ちる」のが当たり前
そして、運命の権利落ち日。 この日、株価は配当金と同じくらいの金額だけ、下落して始まります。
これは、企業の価値が下がったわけではありません。
例えるなら、「ジュースのオマケについていたシールが剥がされた」ようなものです。
シール(配当)がなくなった分、ジュース(株)の値段が下がるのは、ごく自然なことなのです。
この仕組みを知らないと、「何か悪いニュースが出たのか!?」と狼狽売りをしてしまいます。
しかし、これは予め予測できる、いわば「予定された下落」なのです。
フェーズ3:権利落ち後、次のイベントまで株価はどう動く?
権利落ちで下がった株価は、その後どうなるのでしょうか。パターンはいくつかあります。
- すぐに値を戻す(窓埋め)
業績が非常に良い成長企業などは、権利落ちの下げをすぐに埋めるように、株価が回復することがあります。 - しばらく低迷する
配当というイベントが終わってしまい、次の買い材料が見つかるまで、株価がしばらく横ばい、あるいは下落基調になることも少なくありません。
私の保有株の多くが、このパターンに陥ったようです。 - 配当以上に下落する
「配当をもらったら、もうこの株は用済みだ」と考える短期投資家たちの売りが集中し、配当金の額以上に株価が下落してしまうこともあります。
このように、権利落ち後の動きは様々ですが、少なくとも「権利落ち日には株価が下がる」という事実を知っておくだけで、心の余裕が全く違います。
自分の保有株を分析!セオリー通りの動きだったのか?
この一般的なパターンを踏まえて、私の保有株を振り返ってみましょう。
- セオリー通りだった銘柄群
前述の通り、五洋建設(1893)、コプロHD(7059)、オカムラ(7994)、平和不動産(8803)は、9月末に権利落ち日を迎えていました。
これらの銘柄が10月に入って大きく値を下げたのは、まさにこのセオリー通りの動きだったと言えます。 - 配当とは関係なく下落した銘柄も
一方で、サカタインクス(4633)やセルシス(3663)は、配当の権利確定が12月です。
また、フィットイージー(212A)は、まだ配当を出していません。
これらの銘柄の下落は、配当とは関係なく、市場全体の地合いの悪化や、個別の要因によるものだと考えられます。
この分析から分かるのは、「全ての下げが権利落ちのせいではないが、権利落ちが大きな下落要因になり得る」という事実です。
自分の保有株がなぜ下がったのか、その理由を冷静に分析することが、次の投資戦略に繋がります。
まとめ:暴落の「理由」を知れば、投資はもっと楽になる
今回の「+10万円から-6万円へ」というジェットコースター相場は、私にとって非常に痛い経験でした。
しかし、そのおかげで、配当をめぐる株価の動きという、投資のファンダメンタルな仕組みを身をもって学ぶことができました。
- 権利付最終日に向けて株価は上がりやすい。
- 権利落ち日には、株価は配当分だけ下がるのが普通。
- この下落は、企業の価値が下がったわけではない「予定された調整」。
この事実を知っているだけで、突然の株価下落に動揺し、不必要な損切りをしてしまうリスクを大きく減らせます。
むしろ、このサイクルを利用して、「権利落ちで安くなったところを狙って買う」といった戦略を立てることも可能です。
※投資の判断は最後はご自身でお願いします。
投資で心をすり減らさないために、そしてより賢く立ち回るために。
今回の私の失敗談が、あなたの「学び」に少しでも繋がれば幸いです。
はい、すいません
— しきねこ (@Shiki_neko2025) October 1, 2025
調子乗っちゃってました🥲
金曜日+11万から一転、-17,000円😨 pic.twitter.com/lc47arBhJk