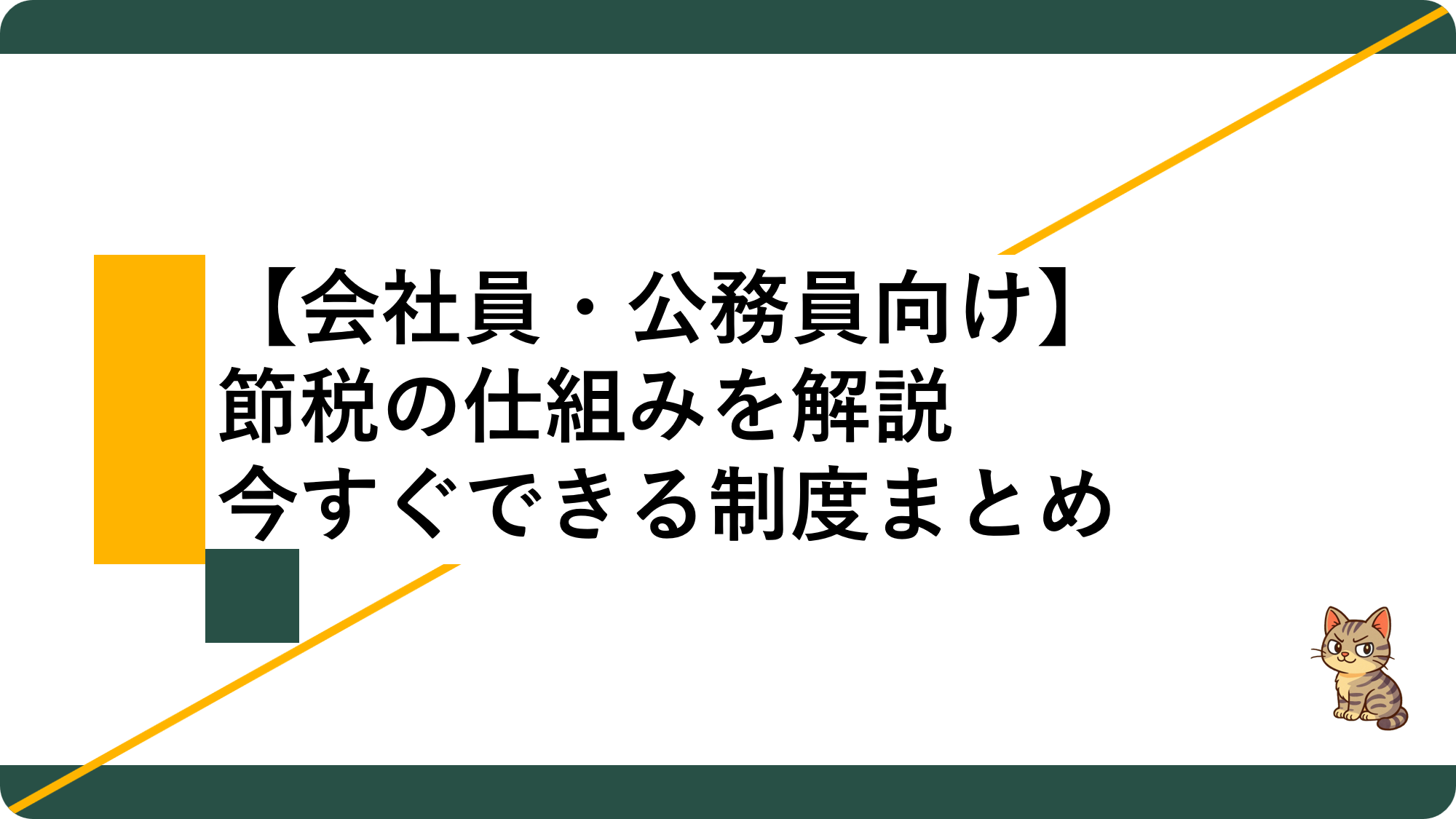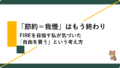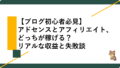毎月、電気代を1,000円削るために、こまめに電気を消す。
その努力は素晴らしいものです。
しかし、もし「仕組みを知る」だけで、毎月5,000円、年間で数万円の税金が合法的に安くなるとしたら、どうでしょうか?
FIREや資産形成を考えるとき、多くの人がまず「節約」に取り組みます。
しかし、私たちが本当に目を向けるべきは、その先にある「節税」です。
「節税」と聞くと、なんだか難しそう、あるいは「ズルいこと」のように感じるかもしれません。
ですが、それは大きな誤解です。
節税とは、ズルをすることではありません。
国が「使っていいですよ」と用意してくれている制度(ルール)を、正しく知って、賢く使うことです。
電気代の節約は「我慢」が伴いますが、節税は「知っているか、いないか」の知識の差だけ。
この記事では、年収400〜700万円台の会社員・公務員の方々が、今すぐできる「節税の基本と実践」について、わかりやすく解説します。
税金の基本。「手取り」が決まる仕組みを知ろう
まず、なぜ税金が安くなるのか、その「からくり」を知る必要があります。
私たちが納める税金は、主に「所得税」と「住民税」です。
この税金の額は、あなたの「年収」にそのままかかっているわけではありません。
「課税所得」という、値引きされた後の金額にかかっています。
計算式はこうです。
- 年収(額面) − 給与所得控除(会社員の必要経費) = 所得
- 所得 − 各種控除(iDeCo、保険料など) = 課税所得
- 課税所得 × 税率 = 税額

難しく見えますが、要は「控除(こうじょ)」という名前の「割引クーポン」をたくさん集めれば、税金の計算元となる「課税所得」が減り、結果的に税金が安くなる、ということです。
節税の基本戦略は、この「控除(割引クーポン)を合法的に増やすこと」。
ただそれだけなのです。
【会社員・公務員向け】今すぐできる節税5選
では、私たちが使える最強の「割引クーポン(控除)」を5つ紹介します。
これらは、ほとんどの会社員・公務員が使えるものです。
1. iDeCo(個人型確定拠出年金):最強の「所得控除」
まず、最強の節税策として知られるのが「iDeCo」です。
これは「自分で作る年金」制度。
- 何がすごい? 積み立てた掛金が、全額「所得控除」になります。
- どれくらいお得? 例えば、年収600万円の人が毎月2万円(年間24万円)をiDeCoで積み立てると、それだけで年間約4万8,000円(所得税20%+住民税10%で計算)も税金が安くなります。
- 注意点 積み立てたお金は、原則60歳まで引き出せません。
とはいえ、実は私はiDeCoは利用していません。
子育てをしている身としては、子どもの成長に柔軟に対応できるようにいつでも引き出せるNISAを主軸にしたいと考えたためです。
正直、この辺はそれぞれの環境に応じて判断すれば良いと思います。
iDeCoも、それはそれでとても有益な制度です。
2. ふるさと納税:実質2,000円で返礼品+税金控除
もはや定番ですが、やらない理由がない制度です。
これは、自分の好きな自治体に「寄付(前払い納税)」をすると、豪華な返礼品がもらえ、翌年の住民税などが安くなる仕組み。
- 何がすごい?
自己負担額は控除上限額以内であれば、実質2,000円。それだけで、寄付した金額に応じたお米やお肉、旅行券などがもらえます。 - 注意点
2025年10月からルールが変更され、仲介サイトのポイント付与が規制されるようになりました。
ふるさと納税制度については、自治体間の競争が過熱していて、制度本来の目的から外れた運用になっていることが多々あります。そのため、時折ルールが厳しくなるように制度改正されることがありますので、ご利用の際にはニュース等で最新情報を確認しておくことをおすすめします。
また、年収や家族構成で控除上限額が決まっているので、まずは自分の上限額をシミュレーターで確認しましょう。
<外部リンク>ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表
我が家では、毎年ふるさと納税でトイレットペーパーやお米といった『日用品』を頼んでいます。必ず使うものを返礼品で貰うことで、節約と節税を同時に実現できる、まさに一石二鳥の制度です。
3. 生命保険料控除・医療費控除:年末調整の再確認
これは、多くの人が「なんとなく」やっている節税です。
- 生命保険料控除
年末調整の時期に、保険会社から送られてくるハガキ(控除証明書)を提出するだけ。生命保険や個人年金保険に入っていれば、一定額が控除されます。 - 医療費控除
年間の医療費が家族全員で10万円を超えた場合(または所得の5%)、確定申告をすれば税金が戻ってきます。ドラッグストアで買った一部の風邪薬や、通院のための交通費(タクシー代など)も対象になることがあります。レシートは必ず保管しておきましょう。
4. 住宅ローン控除:最強の「税額控除」
家を買った人限定ですが、これは最強の節税です。
なぜなら、iDeCoや保険料控除が「所得」から引く「所得控除」なのに対し、これは「税額」そのものから直接引く「税額控除」だからです。
- 何がすごい?
年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、10〜13年間にわたって、納めるべき所得税や住民税から直接引かれます。 - どれくらいお得?
もしローン残高が3,000万円あれば、その年最大21万円も税金が安くなります。これは、他の節税とはケタ違いの効果です。
5. 副業の経費:ブログや副業をしている人へ
もし、あなたが私のようにブログや副業で収入(雑所得)を得ているなら、「経費」を計上することで節税が可能です。
- 経費とは?
その収入を得るためにかかった費用のことです。例えば、ブログ運営のためのサーバー代、ドメイン代、PCの購入費の一部、通信費の一部などを経費として計上できます。 - どうなる?
副業の「収入」から「経費」を引いた「所得」が20万円以下であれば、確定申告は不要です。(住民税の申告は別途必要) もし20万円を超えても、経費を引いた後の金額で税金が計算されるため、大きな節税になります。
【中級編】副業・投資の「ワンランク上の節税」
副業が軌道に乗ってきた方や、投資を本格的に行っている方向けの知識も少し紹介します。
青色申告と白色申告
副業収入が大きくなり「事業」として認められる規模になったら、「青色申告」を検討しましょう。
帳簿付けは複雑になりますが、最大65万円という非常に大きな特別控除が受けられます。
白色申告(簡易な申告)とは比べ物にならない節税メリットです。
「節税」と「脱税」の境界線
経費計上で重要なのは「事業との関連性」です。
友人と食事した代金を経費にするのは「脱税」です。
しかし、その食事が「ブログの打ち合わせ」であったことを合理的に説明できるなら「経費」になります。
この境界線を守ることが、信頼の基本です。
NISAと特定口座の仕組み
投資の世界では、NISAが最強の節税です。
なぜなら、通常、株や投資信託の利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座の中では、それが完全に0円(非課税)になるからです。
多くの人が使う「特定口座(源泉徴収あり)」は、この20.315%を自動で天引きしてくれる便利な口座ですが、税金はしっかり払っています。
節税を考えるなら、まずNISA枠を使い切ることが最優先です。
節税で気をつけたい「落とし穴」
ただし、節税には注意点もあります。
一番の落とし穴は、「節税のために、無駄な支出を増やすこと」です。
例えば、保険料控除の上限に達するために、必要のない保険に新たに入るのは本末転倒です。
税金が1万円安くなっても、保険料で3万円払っていては、差し引き2万円の損です。
節税は、あくまで「必要な支出」を「控除に置き換える」という発想が大切です。
無駄な支出を増やしては、節約の意味がありません。
また、ふるさと納税や確定申告での手続きミスは、かえって損をすることにも繋がるので、慎重に行いましょう。
まとめ:節税は「生活を守るための武器」
お金を貯めるには、「①使わない(節約)」「②取られない(節税・防衛)」ことが大事です。
このうち、会社員・公務員が今すぐ、そして最も効果的に実行できるのが「②取られない」こと、すなわち「節税」です。
税金の仕組みを知ることは、あなたの生活を守るための「武器」と「知識」を身につけることです。
難しそうに見えますが、まずは「ふるさと納税」をやってみる、あるいは「iDeCo」の資料請求をしてみる。
その小さな一歩が、10年後、20年後のあなたの「手取り額」を大きく変えることになるかもしれません。